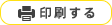こんにちは。坂本です。
今回は、最近社内で起きた「マネージャーの役割定義」についての対話から、組織運営について気づいたことを書きます。
経緯としては、ある日、弊社のマネージャー複数から「マネージャーがやるべき仕事って何なのか、定義してもらえませんか?」という相談を受けまして。
- 部署ごとの役割ではなく、あくまで「マネージャーの役割」を知りたい
- 「部署が違っても共通する」マネージャーの役割を知りたい
とのこと。正直、一瞬「自分で考えてよ…」と思いましたが、良い機会なので深く考えてみることにしました。
- 目次 -
マネージャーの役割とは何か
当社では、すでに「部署ごとの役割分担」を定義しています。その部署が役割を果たすように動くのがマネージャーの役割です・・が、確かにもうちょっと解像度上げられそうですね。
小企業なので皆さんプレイングマネージャーですが、「プレイングじゃないマネージャーの仕事」って何だろう? ということです。
よく言われる3つの機能
一般的によく言われるマネージャーの役割を整理してみました:
1. 経営者の意図を現場に翻訳する
経営方針を「今なぜこれをやるのか」「何を優先するのか」という現場の言葉に言い換える役割。
2. 現場の動き方を設計・調整する
部署の中での業務分担や、仕事のツール・ルールを整備して、仕組みで成果を支える。
3. メンバーの動きと学びを支援する
メンバーの内発的動機を引き出し、成長できる環境を作る。1on1とかもこれに含まれますね。
でも、何か足りない…
これらの機能、確かに間違ってはいないはず。でも、何か物足りない感じがしたんですよね。
それは、これらがバラバラに見えて、つながりが見えないから。
深堀したら「マネジメントの流れ」が見えた
深堀りしたら見えてきた構造
腑に落ちなかったので、いろいろ考えたり、話したりをしました。
マネージャーと話を深めていく中で、「あ、そうか!」という気づきがありました。
マネジメントって、実はこんなサイクルで動いているんだと:
A:顧客価値の実現による売上・利益の確保
目の前のお客さんに満足してもらい、それを売上と利益につなげる。経営者もそのために動いています。なので、いい仕事をして、満足してもらう。これが 全ての起点 です。
B:価値提供プロセスの維持と把握
多分ここが、マネージャー業務の 中核 です。「お客さんを満足させ、売上を作るためのプロセス」をしっかりと実行し、そのプロセスと成果との因果関係を把握する。「満足してもらうプロセス」を自覚して、磨きこんでいくのが大事。「AにつながるB」を磨く。Bから始まるわけではない。
C:プロセスと人材の改善・成長
業務プロセスの改善だけじゃなく、メンバーの育成と成長も進める。個人の成長とチームの成長を両立させていく。大事なんですが、ABのためのCという順番です。Cから始まるわけではない。
D:健全性のチェック(補足)
最近はコンプラとかサステナビリティの話がよく出るので、その観点でDを付け足しました。そのプロセスが社会的に、メンバーにとって、まっとうかどうかを振り返る。ただこれは、AがあってこそのDです。Dから始まるわけではない。
手段を目的と取り違えるから、話がややこしくなる
マネージャーの仕事は「幅広い」と言われます。
あれもこれもそれもどれも大事・っていう話になりがちじゃないですか。メンバーを育成するのが大事、成果を出すのが大事、生産性を高めるのが大事、サステナブルでコンプライアンスなことが大事。
でも、そうじゃない。これらはすべて重要だけど、どれもこれも手段です。
一番大事なのは、目の前にいるお客さんに価値を提供して、満足してもらい、対価を得ること。そのために、いろんな手段がある。さっきの一般論ともつながりました。
- 経営の意図を翻訳する → Aの成果を明確にするため
- 現場の動き方を設計する → Bのプロセスを確立するため
- メンバーの学びを支援する → Cの改善と成長を促すため
つまり、手段だけ見ていて、目的と構造が見えていなかったんですよね。
ただ、まだ画餅な気がする。これだけでは足りない。
ABCDの継続的な改善サイクルを支える「日報」
このABCDのサイクル・・顧客価値提供をゴールとした一連の取り組みは、つながっているので、日々ぐるぐると実行し続ける必要があります。
その際に有用なのが「日報」です。
でも忙しさの中で、そういう気づきって流れていきがち。日報という仕組みがあることで、これらの発見を意図的にプロセス改善やメンバー育成につなげられる。ここがポイントです。
日報とは
どんな業務をしたかだけを書く日報もよくありますが、 弊社の日報は「観察して分かったこと、今後取り組んでいこうと思ったこと」を書いて、他のメンバー全員に共有する 、という形で運用しています。
例えば:
- 「事前に〇〇したときは、問い合わせ対応がスムーズに進み、受注率が上がる」
- 「新人のAさんが同席した〇〇は、意外とお客さんの満足度が高い」
このような日々の発見を、みなが日報に書いていきます。
「A 顧客提供価値」と「B プロセス」の因果関係を見つける
このような日報を書くことで、「今日はこういうプロセスで仕事をして、こういう結果が出た」という記録が残ります。これを積み重ねることで、プロセスと顧客満足・売上の因果関係が見えてくるんです。
日々の仕事の中からこういった事実を積み重ねて、どうやらこういう因果関係があるんじゃないかという発見が得られます。成果を上げる因果関係、あるいは成果が下がる因果関係を見つけて、調整をかけていく。これがAとBがつながった状態です。
メンバーの発見を踏まえて「C プロセスを改善する」
そして、積み重なった体験的事実から、プロセスの改善点を見つけていく。
マネージャーが自ら改善していくのもいいんですけど、メンバーが自分たちで改善できると、もっといいですよね。
なので、マネージャーの役割は、メンバーがこのサイクルを回せるよう支援し、メンバーの主体性・自律性を引き出すことだといえそうです。それが前述のCです。
ただ「メンバーが頑張って何だかチャレンジしている」のが良い状態というわけではなく・・お客さんへの価値提供につながる必要はあります。 発見と観察に基づいて、ABCがつながるのが大事なんだと思います。
実践から学び、学んで実践する
重要なのは、改善のアイデアが日々の実践から生まれるということ。
どこかで見つけた成功事例をそのまま真似るんじゃなくて、お手本は参考にしつつも、自分たちの日々の業務から発見したことを基に改善する。実践して学ぶ。学んで実践する。これを繰り返す。
ちなみに、ピーター・センゲという経営学者の考え方では、こういう「現場の実践から前提を問い直す学習」をダブルループ学習と呼ぶそうです。
学習のループを繰り返すうちに、(1)プロセスが磨かれていく、(2)自らプロセスを磨く能力も高まる、つまり2種類の成長がありますね。そして、それらはより高い顧客満足につながっていきます。
まとめ:マネージャーの本質的な役割
結局、マネージャーの役割とは何だったのか?
それは、「顧客価値の実現を通した利益の確保」を最優先としながら、それを実現するための「結果の出るプロセス」を把握し、プロセスと結果の因果関係を観察して磨いていく。その改善プロセスにメンバーが参加することで、業務改善とメンバーの成長を同時に推進すること、となりました。
一般的に言われる「経営理念の翻訳者」「業務を推進する設計者」「メンバーの成長に伴奏する支援者」という機能も大事。でも、それだとバラバラになっちゃうので。。つながりのある、A→B→C→Dサイクルを回すの仕事だと理解することで、より納得感が高まりました。
ということで、無事話がまとまり、マネージャーの役割定義書のラフができました。そんな感じでマネージャーが仕事していけるよう、今後の進め方を現場で考えてくれています。
腑に落ちないときは、一旦咀嚼してみる
マネージャーの役割とは・・AIに聞けば一発で答えらしきものは出るんですけど、腑に落ちなかったんですよね。
こういうときは、自分の言葉で言い換えてみたり、ああでもないこうでもないと揉んでみると、より自分たちらしい納得のいく定義に辿り着ける気がします。いつもこんな細かいことをしているわけではないんですが、今回はやってみてよかったなと思いました。
「マネージャーの役割定義が優先事項」という会社は全体のごく一部だと思いますが、どんなテーマでも、安易に結論を出さず咀嚼してみるほうが、案外結果としてスムーズになりそう。急がば回れではないなんだろうなーと思いました。
最近は組織周りの相談が増えています。
体制を整えて、良い事業・良い職場を作っていきたい方は、気軽にご相談ください。
ではまた!
「5分でわかるコマースデザイン」をダウンロードする
Q. コマースデザインのEC支援は、何をしてくれるの?
A. コンサル・研修・セミナーを提供しています。支援内容・実績・会社概要を「5分で把握できる」無料資料を作ったので、ぜひご覧ください!
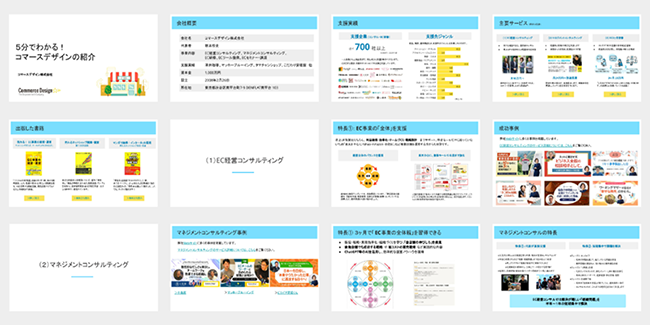
カテゴリー: EC事業の組織論